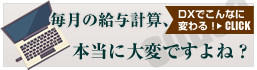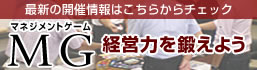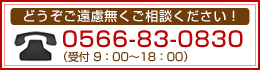GOLGOのひとりごと
見積もりは寿司屋のマインドで 〜アワーレートの落とし穴〜
先日、ある製造業の方から「アワーレートの出し方」について質問を受けました。
私は直感的に、「これは行あたりF、もしくは行あたりMQの話だな」と理解しました。
一体、彼の悩みは何だったのでしょうか?
✅誤解①:固定費と変動費の区別があいまい
まず最初に感じたのは、固定費と変動費の切り分けが正しく理解されていないということ。
変動費とは、販売数量Qに比例する費用だけ。固定費とは、それ以外のすべて。
この基本を押さえていないと、MQのグラフは直線にはなりませんし、当然アワーレートだって正しく出せるはずがありません。
現場でよく見かけるのが、税務会計用の全部原価計算をそのまま使ってアワーレートを算出しようとするケースです。全部原価計算では、Qに比例しない労務費や減価償却費などの「本来は固定費の要素」が原価に混ざってしまうため、MQやアワーレートの概念と相容れません。(MG経験者なら常識ですが・・・)
✅ 誤解②:アワーレートを「見積もりの土台」と考える
次に彼が言っていたのが、「アワーレートをもとに見積もりを出す」という発想。
つまりこういう式です:原価+アワーレート+ 利益 = 見積価格
これには違和感を感じました。この時点で、顧客の事情も、競争環境も、価値の感じ方も一切無視されているからです。
✅ MGの教訓:価格は毎回変えていい
MGでも期首の経営計画では「行あたりMQ」などの指標を使って戦略を立てますが、それはあくまで“参考”であり、“縛り”ではありません。
競合が少ないなら高値で売ればいい。
競合が多いなら価格を下げるか、そもそも売らない選択もある。
(それが許される状況なら)価格は市場や局面に応じて臨機応変に決めるべきです。
✅ 社員にMGを学ばせる意義
会社の上層部がアワーレートを提示した瞬間に、責任を問われたくないサラリーマンはこれを“絶対基準”として認識してしまいがちです。その結果辿り着くのが「平均値という正義」です。
これは正義でもなんでもありません。
この正義には(迷信にはよくあることですが)隠れた前提があります。
「利益はすべての商品・すべてのお客様から均等に得られなければならない」
請求書を切る業種(=受注販売)で小売店のように公示価格は必要ありません。むしろマージンは、得やすいところからは多く得て、得にくいところでは無理をしない。それが戦略です。それをやらずに「平均値という正義」にすがりつくのは単なる手抜きです。社員にMGを学んでもらう意義はこういうところにあるのです。自腹を切った経営者が決してやらないような手抜きをさせないために。
✅ 見積もりは寿司屋のマインドで!
たとえば「時価」の寿司屋があったとしましょう。
A:ひとりで来た常連
B:団体客
C:女性同伴で来た見栄を張りたい男性客
これらすべてに同じ価格を提示する寿司屋は、商売が下手です。
Cには見栄を利用して高く取る。
Bにはキリのいい値段で割引感を出す。その代わり、料理はほどほどで十分。
Aには最高の素材を、感謝を込めて丁寧に出す。
お客様の状況を見て、最適な値付けとサービスを考える。これが本当の「おもてなし」ではないでしょうか。
✅ 結論
アワーレートを出すなとは言いません。
ただし、それを「見積価格の基礎」として盲信するのは危険です。
工場は寿司屋と違ってお客様の顔が見えませんが、実際に買ってくれる相手は人間なのです。
価格は、市場の状況・顧客の価値観・競合環境を見て決めるもの(これを3C分析といいます)。
これは平均値のような単純な式ではなく、ひとりひとりの心を想像してベストプラクティスを探す高度な営みです。
経営の現場には、アワーレートや全部原価計算のような思考停止の迷信がゴロゴロ転がっています。
私たちはそれらを廃して、経営の本質を学び続ける必要があります。
お気軽にご相談ください

「GOLGOのひとりごと」カテゴリ一覧
会社を守る!・リスク管理
- 残業代をめぐるトラブルの防止策①
- 残業代をめぐるトラブルの防止策②
- 「雇用契約書」が大切な本当の理由①
- 「雇用契約書」が大切な本当の理由②
- 企業が持つべきソーシャルメディア「防衛策」
- 社会保険協会への入会は義務ではありません
- 年金事務所の調査が増えています
- 業務上事故の使用者責任
- 現場から見た労使紛争の治療と予防
- ネット社会における内部告発対策
- 配置転換による給与の引き下げ
- 管理監督者とは?
- 資格取得費用の返還請求
- 無断で残業された場合の残業手当は?
- 社員にペナルティを課すには
- 出向に関する労働者の同意
- 職種の変更はできる?できない?
- 過労で社員が自殺したら、会社の責任?
- 社員が過労死したら会社の責任?
- 内部告発にどう対応するか?
- 社員が裁判員に選ばれて仕事を休まれたら?
- 休職を繰り返すうつ病社員への対応
- 社内不倫を理由に解雇できるか?
- 外部の労働組合から団体交渉を申し込まれたら?
- 「検索文化」が労使トラブルを助長する?
- 接待でお酒を飲む事は業務と認められるか?
- 社会保険の調査で調べられること
- 賃金や労働時間などの労働条件は口頭の説明だけでよいか?
- 仕事中にケガをした場合の対応
- 社員を他の店舗へ転勤させるときの注意点
- 社長の労災
- セクシュアル・ハラスメントの境界線
- 派遣と請負の違いは?
- 労働基準監督署の臨検とは?
- 労働基準監督官の持っている権限とは
- 遅刻の多い社員への対応
- 副業を禁止できるか?
- 労基署の臨検で違反が発覚したら?
- 派遣社員が仕事中にけがをした場合
- 家族従業員の扱い方
- 通勤経路の重要性
- 休憩時間中のケガと労災保険
- 健康診断の義務
- 退職社員と守秘義務
- 労災保険に入ってないのに労災事故が起きたら?
- 社員が勤務中に倒れた場合、労災は?
- 契約社員に辞めてもらう際の注意点
- タイムカードは無い方が良い?
- 退職の多い時期に退職を防ぐ対策
- 従業員の身辺調査はどの程度許されるか?
- 研修時間は労働時間か?
- 音信不通の社員への対応
- メンタル疾患の労災認定
- 解雇の有効・無効
- 退職勧奨の注意点
- 労働組合法を知ってますか
- 解雇が無効になった場合の金銭支払
- パワハラの定義について
- 協調性のない社員を解雇できる?
- 自主的な残業への残業手当問題
- セクハラ対策
- セクハラの定義
- 労働組合からの団体交渉
- 団体交渉の注意点
- 人事労務の環境整備不足は「負債」である
- 監督署の調査の種類
- 年金事務所の調査
- 休職者の職場復帰をどう判断するか?
- 有期雇用契約の注意点1
- 有期雇用契約の注意点2
- 賃金構造基本統計調査には協力せねばならない?
- 過重労働撲滅特別対策班
- 試用期間に問題社員を解雇する場合
- パワハラとは
- 無断欠勤!無断遅刻!
- 上長の指示に従わない社員への対応
- 社員が自主的にサービス残業していると会社は罰せられるか?
- アルバイトの労災保険
- 出張や社員旅行などで泥酔してけがをした場合に労災保険は使えるか?
- 研修中の安全配慮義務
- 通勤中にケガをしたら
- アルバイトやパートにも雇用契約書が必要か?
- 通勤災害とは
- 退職勧奨と解雇は同じではない件
- 注意するとパワハラ呼ばわりする社員
- 遅刻や無断欠勤への対処
- 社員が会社のお金を横領・窃盗したら?
- インフルエンザにかかった社員への対応
- SNSの発信を会社が取り締まることができるか
- 精神疾患のため休みがちな社員への対応
- 年金事務所の調査のポイント
- 仕事の後の飲み会は残業扱いになるか
- 資金繰りとキャッシュフロー計算書の目的
- 過労死と会社の責任
- 固定残業制度
- 算定基礎届・年金事務所の調査
- 休職制度は必要か?
- 建設業の労災保険
- 社員に損害賠償を請求できるか?
- 労働条件の不利益変更
- 労災の業務起因性と業務遂行性①
- 労災の業務起因性と業務遂行性②
- 労災保険のメリット制
- 在宅勤務中の労災
- 始末書の目的と役割
- 茶髪や派手な服装での出社をやめてほしい
- ブログやツイッターに会社の悪口を投稿したらクビになる?
- セクハラ防止と対応方法
- 社内不倫と解雇
- 通勤手当の不正受給
- 社員を雇った時の書類
- 従業員の業務外の非行
- 社内恋愛を禁止できるか?
- 賞与を支給する対象者は会社が決められる?
- 「社内恋愛禁止令」は有効か?
- 妊産婦、育児中の労働者の取り扱い
- 均衡待遇と均等待遇の違い
- 会社主催の宴会で暴行事件が起きたら
- 従業員のメールやパソコンを監視して良いか
- 有給休暇の理由を聞いてもいいか?
- 労働組合
- 海外療養費
- 私生活の素行の悪さについて
- 連絡の取れない無断欠勤中の従業員への対応
- 仕事中の熱中症は労災か?
- 労働時間の適正な把握&措置
- 賃金台帳と労働者名簿
- 解雇とは?
- 管理職の残業手当
- 労災発生時の対応
- 以前の保険証を使って医者にかかった場合
- インフルエンザに社員が掛かったら?
- 通勤災害は労災か自賠責かどちらがいいか?
- 育児休業を開始する社員に対し、職場復帰を確約する誓約書を提出させることはできるか。
- 精神障害の労災認定基準
- 転籍は拒否できるか
- 新型コロナウイルスについてのQ&A
- 使用人兼務役員の年次有給休暇の取扱について
- もしも従業員がコロナに感染したら?
- 給与を取り来ない従業員がいた場合の対処方法
- コロナで労災申請はできるか?
- 未払い残業代請求訴訟における「付加金」
- セクハラと労災
- 求人票に固定残業代を記載する時の注意点
- 未払い残業代を遡って支払った場合の社会保険料
- 労災給付の申請書に医師証明書をもらう場合の診断書料について
- 労働保険料申告手続きを忘れたら?
- お上はある日突然動く!
- パワハラ防止指針
- 雇用契約と業務委託契約
- 給与から控除できる項目
- 源泉所得税の甲欄乙欄
- 社会保険の適用事業所と加入者について ~その2~
- 退職者が引継ぎをせず、有給消化を申請した場合の対応
- 業務上のミスで発生した損害を折半することを約束した労働条件は無効か
- 妊娠中の軽易な業務への転換
- 整理解雇の4要件を知ってますか?
- 会社都合で1日の所定労働時間の一部を休業させた場合の休業手当
- テレワーク時の時間管理について①
- 不当労働行為
- 就業規則の持ち出しを禁止してもよいか?
- 労働保険料等の納付猶予
- 労働基準法上の賠償予定の禁止
- 副業・兼業の促進に関するガイドライン
- 社員が濃厚接触者となった場合の取扱い
- 退職が決まっている社員の賞与
- リモートワークでの労働時間の管理方法
- 問題社員を解雇する方法
- 労災保険の費用徴収
- 罰金制度の注意点
- ハラスメントをしてしまうのは悪者よりも愚か者
- 固定残業手当の注意点
- 労働審判という制度について
- 労働組合の団体交渉とは
- 中小企業におけるパワハラ防止措置義務
- 問題社員への退職勧奨を行う前に気を付けること。
- 退職の種類
- 複数の事業所で雇用される場合の社会保険
- パワハラ対応で感じたこと
- 割増賃金計算に算入すべき手当、除外可能な手当の概要
- 割増賃金計算に算入すべき手当、除外可能な手当の実態とは
- パワハラ対応におけるTOC
- 労働時間把握のガイドライン(労働時間とは)
- 労働時間の把握ガイドライン(把握の方法)
- 労働時間の把握ガイドライン(自己申告の場合の措置)
- ホテル時代の元上司の話
- 業務効率の悪い社員には残業手当を払わなくても良いか?
- ついに51人以上の企業のパートに社会保険の適用が拡大されます
- プロフェッショナルに労基法はいらない
マネジメントゲーム
- マネジメントゲーム受講のきっかけはお客様の倒産
- 初MG(最初の一回で止めるつもりだった)
- 初MGで散々な目に遭うも、悔しさのあまり再挑戦!
- 西順一郎先生と出会い、目から鱗が落ちた初めての2日間MG
- 講師をやるつもりは更々なかったが・・・
- 愛環MG.2012.9
- ガンを克服してホノルルマラソンを完走した大先輩もMG経験者だった
- なにわMGに参戦
- MGの収穫①『投資的発想を持つ』
- ゴルゴMG(4月)開催報告
- MGの収穫②「Y理論」
- 初めて息子を参加させた1卓開催のMG
- 初心者12名のMG
- 親子MGに参加
- ゴルゴMG(5月)開催報告
- ゴルゴMG(8月)開催報告
- 5期A卓での戦い方
- ゴルゴMG開催報告2014.11.23
- ゴルゴMG開催報告2015.2.28
- ゴルゴMG開催報告2015.5.17
- ゴルゴMG開催報告2015.8
- ゴルゴMG開催報告2015.10
- 金沢MG(名物インストと非常に独特な北陸ルールを体験)
- ゴルゴMG開催報告2016.3
- キャッシュフローMG(CFMG)開催報告2016-9
- MG300期!
- MGの決算で自信を持てるようになる方法
- 来年2月に平日MGを開催します!
- 慌てることと急ぐことの違い
- MGの収穫③「言語を選択することの重要性」
- 資金繰りとキャッシュフロー計算書の目的
- MGの収穫④「横着と愚直」
- MGインストラクターの目的と手段
- MGの収穫⑤「主体性は教えることができない」
- ゴルゴCFMG開催報告2018.7.15
- 小さな会社の強味を生かす方法をMGでやってみた
- 大阪の萬集楼さんにてCFMGを開催!
- 簿記3級を試験勉強一日でクリアする方法
- 1日コースか2日間コースか?
- 決算でミスを発見する方法
- 中小企業の人材獲得戦略
- MGの記帳で焦らないようにする方法
- 社長、夜ぐっすり眠れてますか?
- 決算はドライバーではなく、パターを打つようにやる
- 緊急事態宣言下ですがゴルゴMG開催しました
- 高学歴の人でもMGの決算に手こずるのはなぜか?
- 愛知県に緊急事態宣言が発令されましたが・・・。
- 新しい用紙で決算をやり直してはいけない理由
- 環境は意思よりも強し!
- わからない人同士での教え合い
- 8年ぶりの古河MG
- 古河MG4期の経営計画発表会
- CFMG開催報告2021.11
- マトリクス会計表の間違いの見つけ方には2つのモードがある
- 1200期達成おめでとうございます!
- 小学生にもわかる会計のお話
- ビジネススクールとマネジメントゲームの違い~どんな人にMGが向いているか~
- MGで会計を学ぶと10倍速い理由
- 何のためにMGをやっているか。
- 初めての最優秀経営者賞-10年前の愛環MG-
- MGの決算と真善美
- 記帳できていないのに自分の順番が回ってきたら、どうすればいいか?
- インストラクターがやってはいけないこと
- 古河MG3期、残り1行の入札
- 初MGの舞台が幕を閉じる時
- 運命神ヤーンと出会いの法則について
- MG for students(知立市)開催報告
- 気付きを得るために必要なこと
- 初心者MGから見えるのは人間の本質
- MG for Students刈谷 開催報告
- 子供の壁と行入のチカラ
- MG for Students大府市 開催報告
- 私とCFMG
- 古河MGで2年ぶりに表彰状
- 有給休暇管理表の上手な作り方
- MG for Students東海市 開催報告
- 長浜MG~近江牛に想い出を添えて~
- M型職種とQ型職種
- 福井MG 育児休業 好奇心
- 良い借金、悪い借金
- MGの決算はなぜ手書きなのか?
- MG for Students安城 開催報告
- 凡人が頭を上手に使う方法
- 名古屋MG0.5期にて「MG流の教育とは」
- MG for studentsはクリティカルビジネスたり得るか
- 三洲MG道場
- ある日のAIとの対話「信用の複利とウインウイン思考の可能性」
- トランプ時代とMG
- トランプ・ゼレンスキー会談から学べること
- 決断力の正体を探る
- 見積もりは寿司屋のマインドで 〜アワーレートの落とし穴〜
- MG for Students 刈谷市・安城市 開催レポート
- MG for students豊田 開催報告
- MG for students名古屋 開催
- 「成績より向上」の本当の意味 〜成長するために本当に必要なこと〜
- ベテランが初心者から学ぶMG
- 信用とCFMG
- CFMG開催報告2025.12
- ゴルフとMGが教えてくれる「素直さの本質」
- Noteはじめました!
給与計算・賃金の取り扱い
- 給与計算の不徹底は穴の開いたバケツ
- 今から準備したい年末賞与 Q&A
- 給与の締め日や支払日は会社の任意に変更できるか
- 賃金支払いの5原則の話
- 休業手当の未払いにご用心
- 会社都合で休業をする場合の補償
- 給与から親睦会費や互助会費などを天引きする時の手続きについて
- 平均賃金
- 賃金の支払い形態の話
- 残業代の定額支給はアリ?
- 就業規則変更による賃金引き下げの話
- 休日の出張旅行は休日出勤?
- 管理職の割増賃金
- 減給の上限
- 会社から一方的に給与を下げることはできるか?
- 残業手当の基になる賃金
- 仕事を覚えるまでの賃金を低く設定してもよいか
- 感染症にかかった社員の自宅待機中の給与
- 合法的に給与を下げる方法
- 着替えの時間は労働時間とすべきか?
- 割増賃金から除くことができる手当
- パートの残業代計算の注意
- 出張先への往復移動時間の給与
- どこまでが賃金か?
- 社会保険料が変わる月です!
- 賞与、退職金は会社の義務か?
- 残業代の未払いと過払い
- フルコミッション給与制度の問題点
- 割増賃金の計算
- 年俸制の話
- 社員旅行積立金を給与から天引きしてもいいか?
- 給与支払日の変更時に気を付ける事
- 固定残業手当導入の注意点
- 最低賃金はどう決まるか
- 取引先の接待で飲食をしている時間は残業か?
- 遅刻に対して余分に賃金をカットできるか?
- 割増賃金
- 昼休みの電話番は労働時間か?
- 雇用保険料率が変更されました!
- 月60時間以上の残業は割増賃金が高い?
- 子供を産んでいる期間中の給与
- 住宅手当と残業代計算
- 労災の最初の3日は補償されない?
- 通勤手当には非課税限度額があります。
- 60歳を過ぎて再雇用した社員の給与はそれまでよりも下げていいのか?
- 最低賃金制度とは
- 非課税の交通費には限度額がある
- 定年後再雇用の給与
- 労働保険の一元適用と二元適用
- 給与からの控除のルール
- 賃金の5原則
- 健康診断の費用負担とその間の賃金
- 賃金の注意点
- 2以上の会社から報酬を受けている場合の社会保険料
- 就労時間後の飲み会は残業か?
- 年末調整
- 賞与にかかる社会保険料
- 賞与は義務か?
- 給与締日、支払日の変更
- 最低賃金に関する法律
- 深夜割増賃金
- 在宅勤務のみなし労働時間
- 賞与を支給する対象者は会社が決められる?
- 残業代の計算
- 日々の所定時間を変形させると有休手当の計算でつまづく可能性大
- 降格により減給する場合の金額の限度
- ダブルワーカーを雇用した場合の時間外割増の計算
- 休職中の住民税
- 労働保険の年度更新
- 算定基礎届について
- みなし残業代制度とは
- 最低賃金と労働時間
- 社会保険の喪失日と保険料の関係
- 管理職の残業手当
- 残業手当の単位
- 慶弔休暇は有給か無給か?
- 慶弔見舞金
- 有給休暇の賃金の計算
- 未払い残業代を遡って支払った場合の社会保険料
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
- 給与から控除できる項目
- 調査で判明する社会保険の誤解
- 退職者が引継ぎをせず、有給消化を申請した場合の対応
- 歩合給がある場合の残業計算
- フレックスタイム制における休日割増賃金
- 平均賃金の基本的な考え方
- 会社都合で1日の所定労働時間の一部を休業させた場合の休業手当
- テレワーク時の時間管理について②
- 自転車通勤者の通勤手当
- 退職が決まっている社員の賞与
- 固定残業手当の注意点
- 社宅を貸したときの所得税
- 毎月の給与計算、本当に大変ですよね?
- ムダな振込手数料を払っていませんか?
- 一度体験したら二度と元のやり方に戻りたくなくなる便利な振込のやり方
- 給与計算はタテ割よりヨコ割が便利!
- 有給休暇管理表の上手な作り方
- 業務効率の悪い社員には残業手当を払わなくても良いか?
就業規則
- 休職期間の話
- 競業避止と職業選択の自由の話・1
- 就業規則の不利益変更
- ルールのない会社で起こること
- 就業規則の話①
- 就業規則の話②
- 就業規則の話③
- 就業規則は誰に効くか?
- 就業規則変更による賃金引き下げの話
- 管理職の割増賃金
- 休職を繰り返すうつ病社員への対応
- 社内不倫を理由に解雇できるか?
- 職種によって定年年齢を変えても良いか?
- 社員が裁判員となった時の取り扱い
- 「退職証明書」の話
- 親の介護で休みたいとの申し出があったら?
- 社員を他の店舗へ転勤させるときの注意点
- 休職制度とは
- なぜ社員は社長のように考えられないのか?(企業にとっての憲法論)
- 社員が逮捕されたら?
- 個別の社員の労働条件を変えていいか?
- 解雇にもいろいろある
- 就業規則は社員の意見を聞いて作らなくてはならない?
- 経歴詐称は懲戒解雇できる?
- 就業規則を変更することで給与を下げられるか?
- 就業規則が有効であるためには条件がある
- 懲戒処分について知ってますか?
- 就業時間中の私用メール
- 会社合併時の労働条件をどう合わせるか?
- 休職制度の運用
- 通勤手当の注意点
- 自主的な残業への残業手当問題
- 会社の備品を持ち帰った従業員
- 従業員から休職を申請されたら
- 半日単位の有給休暇
- 懲戒処分を段階的に行う
- 社内恋愛を会社が禁止できるか
- 1ヶ月単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 経歴詐称の社員を解雇できるか
- 競合他社へ転職した社員の退職金
- 1か月単位の変形労働時間制
- 身だしなみに問題がある社員
- 遅刻や無断欠勤への対処
- 社員が会社のお金を横領・窃盗したら?
- 懲戒処分(ペナルティー)を与えるには
- 就業規則は作っただけでは効かない
- 休職制度の意味と運用
- 固定残業制度
- 退職金を減額したい
- サマータイム制に必要な法的手続
- 休憩時間中の「電話番」
- 能力不足で社員をクビにできるか?
- 労働条件の不利益変更
- ブログやツイッターに会社の悪口を投稿したらクビになる?
- セクハラ防止と対応方法
- 社内不倫と解雇
- 出張の移動時間は労働時間になるのか?
- 社内恋愛を禁止できるか?
- 労働時間をみなす制度
- 休業手当
- 賞与を支給する対象者は会社が決められる?
- 「社内恋愛禁止令」は有効か?
- 残業代の計算
- 日々の所定時間を変形させると有休手当の計算でつまづく可能性大
- 従業員のメールやパソコンを監視して良いか
- 降格により減給する場合の金額の限度
- 就業規則の届出手続き
- 就業規則の記載事項
- 従業員代表の適法な選出
- 給与を取り来ない従業員がいた場合の対処方法
- 育児休業中に有給休暇を取得可能か?
- 就業規則の持ち出しを禁止してもよいか?
- 罰金制度の注意点
- ハラスメントをしてしまうのは悪者よりも愚か者
- 退職の種類
助成金・貰えるお金
- 雇用促進税の活用について
- 傷病手当金の話
- フリーター対策・雇用の助成金(4年間460万円)
- 育児休業中の保険料免除
- 退職後の傷病手当金・出産手当金の話
- 毎月15万円の助成金①
- 若者チャレンジ奨励金のOFF-JTを減らす方法
- 職場意識改善助成金が骨抜きになった理由
- パートの正社員への登用制度
- 定年後の雇用保険給付
- 両立支援等助成金の出生時両立支援コース
- 育児休業給付
- 育児休業支援コース助成金
- 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
- 育児休業中に仕事に出た場合の給付金はどうなるか?
- 雇用関連の助成金
- 年金の脱退一時金
- 失業保険はいくらもらえるか
- 入社直後に傷病手当金を申請できるか?
- 令和3年5月・6月の 雇用調整助成金について
- 助成金 育児休業等支援「新型コロナウイルス感染症対応特例」
- 新型コロナウイルスの影響によるシフト減少で離職した場合の求職者給付
- 令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置
- キャリアアップ助成金2022年4月変更点
- 雇用調整助成金の不正受給対応が厳格化されます!
制度を上手に活用
- 社会保険の被保険者について
- 再就職手当の話
- 国民年金の被保険者の種類
- 失業保険と年金の話
- 国民年金保険料を滞納した場合の障害年金の話
- 国民年金の免除
- 出産・育児にかかる給付金
- 高額療養費制度の話
- 在宅勤務について
- 在宅勤務者の労働時間
- 仕事中の交通事故
- 休憩時間中のケガと労災保険
- フレックスタイム制の注意点
- 退職後の社会保険手続き
- 労災の休業補償
- 育児休業
- 介護休業
- 1ヶ月単位の変形労働時間制
- 高年齢雇用継続給付を活用しましょう。
- どんどん手厚くなる育児休業給付!
- 役員の雇用保険
- 労災の最初の3日は補償されない?
- 育児のために短い時間働きたい場合。
- 労災給付の種類
- 健康保険は会社を辞めた後も続けられる?
- 高額の医療費が掛かった時に受けられる制度
- フレックスタイム制をわかりやすく
- 1か月単位の変形労働時間制
- 保険証が届く前に病院にかかるとき
- 退職後の傷病手当金
- 退職後の健康保険給付
- 育児休業給付
- 確定拠出年金
- 高額療養費と限度額認定
- 労災保険はどこまで使えるか?
- 健康保険の被扶養者
- ユースエール認定制度
- 健康保険の給付
- 建設業の労災保険
- 労災保険のメリット制
- 雇用保険の再就職手当
- 高額な医療費がかかった時にもらえる給付
- 在宅勤務中の労災
- 雇用保険の基本手当日額
- ストレスチェックの 助成金
- 失業時の給付が手厚くなる条件
- 再就職手当
- 年金の受給資格期間
- 産前産後休業の保険料免除制度
- 在宅勤務のみなし労働時間
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
- 傷病補償年金とは
- 労災保険の特別加入
- 雇用保険の適用拡大(その2)
- 高額療養費と限度額適用
- 海外療養費
- 教育訓練給付金
- 未払い賃金建て替え払い制度
- 育児休業中の社会保険料免除
- 両立支援等助成金の出生時両立支援コース
- 災害時における労働時間及び休日出勤
- 労災発生時の対応
- 育児休業給付
- 育児休業支援コース助成金
- 療養費の払い戻し請求
- 月額変更の年間平均を用いた申し立て制度
- 有給休暇の基準日の設定
- 振替休日と代休
- 新型コロナウイルス感染時の傷病手当金
- 海外在住親族の健康保険の扶養手続
- 育児休業中に仕事に出た場合の給付金はどうなるか?
- 労働保険事務組合って何?
- 教育訓練給付の拡充
- 非常勤役員の社会保険加入
- 休業等があった場合の算定基礎届の考え方
- 社会保険の住所変更
- 雇用関連の助成金
- 休業手当を支給した月が含まれる場合の離職証明書の書き方
- 男性の育児休業の注意点
- 別居している被扶養者の認定
- 第1子育児休業中に第2子を妊娠した場合
- 源泉所得税の甲欄乙欄
- 新型コロナウイルス感染時の傷病手当金受給について
- 年金の脱退一時金
- 高齢者医療制度
- 離職票の発行義務について
- 入社直後に傷病手当金を申請できるか?
- 労働保険料等の納付猶予
- マイナンバーカードの健康保険証利用について
- 出産や育児にかかる社会保険料の免除
- 産休中の国民年金保険料免除
- 育児休業中の就労
- 労災で休業した日に賃金を払ったら休業補償の計算は?
- 新型コロナの影響による特例月額変更の延長
- 労働審判という制度について
- 外国人が帰国した際の年金はどうなる?
- 社保適用拡大に合わせたパートタイマーへのヒアリングについて
休日・休憩・休暇
- 有休を我慢させるのは会社にとって損か?得か?
- 休憩時間の話
- 年次有給休暇の話①
- 有給休暇は本当に社員の希望した日に与えなくてはならないのか?
- 休日と休暇の違い
- 休憩の自由利用の原則と例外
- 退職時の有給一括取得は拒否できるか?
- 有給休暇を時間単位で取らせる方法
- 休憩時間の考え方
- 産前産後休業の話
- 有休取得を会社は拒否できるか?
- 欠勤日の有給振替
- 退職する社員が有給休暇をまとめて取ることは回避できるか?
- 法定労働時間の原則と例外 その1
- 法定労働時間の原則と例外②
- 「法定休日」と「法定外休日」
- 休憩についての法律
- 取引先の接待で飲食をしている時間は残業か?
- 半日単位の有給休暇
- 育児休業
- 介護休業
- 掃除時間は労働時間か。
- 昼休みの電話番は労働時間か?
- 子供が病気になったら会社を休めるか?
- 就労時間後の飲み会は残業か?
- 定年後再雇用、有給休暇の扱い
- 有給休暇の比例付与
- 慶弔休暇は会社の義務か?
- 休日と休暇はどう違うか?
- 出張の移動時間は労働時間になるのか?
- 夏休みや冬休みを有休消化日にできるか
- アルバイトにも有休?
- 有給休暇の理由を聞いてもいいか?
- 産前産後の労働者への対応
- 有給休暇の基準日の設定
- 慶弔休暇は有給か無給か?
- 定年退職後の再雇用者に対する有給休暇の考え方
- 使用人兼務役員の年次有給休暇の取扱について
- 退職者が引継ぎをせず、有給消化を申請した場合の対応
- 従業員が休憩を取らない代わりに、早く帰りたいと希望した時の対応
- 子の看護休暇と介護休暇の時間単位取得
- 週休3日制の導入についての考察
- 有給休暇管理表の上手な作り方
雇用の入り口と出口
- トラブルを予防する雇用契約書の書き方のコツ① (転勤)
- トラブルを予防する雇用契約書の書き方のコツ② (試用期間)
- 解雇の話①
- 解雇の話②
- 整理解雇の4要件
- 私生活上の犯罪・非行に対する解雇は有効かどうか?
- 問題社員の解雇①
- 問題社員の解雇②
- 健康保険の任意継続制度
- 試用期間の話
- 広告と異なる条件での労働契約
- 妊娠・出産を機に解雇してもよいか
- 退職社員への賞与は必要か?
- 退職願の撤回はできるか?
- 試用期間の延長はできるか?
- 内定取り消しはできる?
- 社員は転勤命令を拒否できるか?
- 労働者からの退職申し出期間
- 社内不倫を理由に解雇できるか?
- 職種によって定年年齢を変えても良いか?
- 求人募集の注意点
- 試用期間と契約期間
- 賃金や労働時間などの労働条件は口頭の説明だけでよいか?
- 「退職証明書」の話
- 仕事を覚えるまでの賃金を低く設定してもよいか
- よく似た言葉:退職願と退職届
- 社員が行方不明になったら?
- 解雇にもいろいろある
- 退職社員と守秘義務
- 契約社員に辞めてもらう際の注意点
- 試用期間中に解雇する場合の注意
- 契約社員の契約満了時の注意
- 引き継ぎ不十分の社員に退職金を払わなければならないのか?
- 転勤拒否した従業員を解雇できるか?
- 出向は同意が必要?
- 解雇の有効・無効
- 退職の申し出は撤回できる?
- 有期契約労働者の雇止め
- 整理解雇の対象者は会社が選べるか
- 会社が負担した外部研修費用の返還請求
- 「業務委託」と「雇用」の違い
- 行方不明になった社員を解雇にできるか
- 自己都合退職の撤回
- 経歴詐称の社員を解雇できるか
- 無断欠勤の社員は解雇できるか?
- 解雇予告手当とは?
- 入社時に提出させるべき書類
- 入社してすぐに辞めた社員の離職票
- 解雇の撤回
- 試用期間に問題社員を解雇する場合
- 退職勧奨と解雇は同じではない件
- 能力不足の社員を辞めさせることはできるか?
- 定年後再雇用、有給休暇の扱い
- 社会保険の資格取得日と喪失日
- 退職金を減額したい
- 競業避止
- 雇用保険の再就職手当
- 失業時の給付が手厚くなる条件
- 社員を雇った時の書類
- 試用期間中の社会保険
- 経歴詐称と内定取り消し
- 連絡の取れない無断欠勤中の従業員への対応
- 解雇とは?
- 雇用保険の手続き終了後に誤りがあった場合の対処法
- 転籍は拒否できるか
- 試用期間の延長はできるか
- 外国人を雇用する際の注意点
- 雇用契約と業務委託契約
- 業務上のミスで発生した損害を折半することを約束した労働条件は無効か
- ワーキングホリデーで滞在する外国人の保険加入
- 整理解雇の4要件を知ってますか?
- 離職票の発行義務について
- 自己都合退職の場合の給付制限期間の短縮
- 士業事務所の社会保険の適用要件が変わります
- 64歳と65歳の失業保険の違いは?
- うつ病による通院歴を隠して入社する行為は履歴詐称か
- 新型コロナウイルスの影響によるシフト減少で離職した場合の求職者給付
- 外国人が帰国した際の年金はどうなる?
- トランプ時代とMG
採用・教育・社員力強化
- 最初のひとりを雇う時
- 採用に役立つ適性診断を活用していますか?
- 人材の選び方
- 「パワハラ」と「熱血指導」の境界線とは
- 目的ある「OJT」の設計
- 学生をアルバイトに雇う時の注意点
- 採用選考時に病歴を尋ねてもよいか
- 会社が負担した外部研修費用の返還請求
- 内定辞退者への損害賠償請求
- 社内教育の在り方について
- 数学の勉強の仕方
- 始末書の取扱い
- 試用期間に問題社員を解雇する場合
- 無断欠勤!無断遅刻!
- 上長の指示に従わない社員への対応
- 採用面接時に聞いてはいけないこと
- 経歴詐称について
- 募集時に性別を限定しても良いか?
- 能力不足の社員を辞めさせることはできるか?
- 「会社側の」面接
- 中小企業の人材獲得戦略
- 緊急事態宣言下ですがゴルゴMG開催しました
- 採用!採用!採用!
- 配慮すべき個人情報とは
- アイデア募集する側に求められる配慮とは?
- MG for Students大府市 開催報告
- 能力と人格の関係
社会保険料・コスト削減!
- 社会保険料変更の仕組み
- 労働保険年度更新の基礎知識
- 雇用保険料の使われ方
- 建設業の労働保険料が4割引!
- 雇用保険の手続を忘れてしまったら?
- 国民健康保険+厚生年金の社会保険
- 雇用保険に加入しなくてはならない人
- 社会保険の加入期間、保険料
- 社会保険の加入期間と保険料徴収
- 産前産後休業期間中の社会保険料免除
- パート、アルバイトの社会保険適用
- パートタイマーへの社会保険適用拡大
- 事業所の社会保険適用状況がWEBで検索できる?
- 労働保険の年度更新
- 借り上げ社宅と社会保険
- 雇用保険・最初の手続
- 社会保険・算定基礎届
- 賞与にかかる社会保険料
- 育児休業中の社会保険料免除
- 月額変更の年間平均を用いた申し立て制度
- 役員の社会保険加入
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
- 標準報酬月額の特例改定
- 調査で判明する社会保険の誤解
- 第1子育児休業中に第2子を妊娠した場合
- 社会保険の適用事業所と加入者について ~その1~
- 自動車通勤者の通勤手当
- 源泉所得税の甲欄乙欄
- 社会保険の適用事業所と加入者について ~その2~
- 労働保険料等の納付猶予
- 個人士業の社会保険
- ムダな振込手数料を払っていませんか?
- ついに51人以上の企業のパートに社会保険の適用が拡大されます
制度の見通し・世の中の動き
- 注目すべき厚生年金の「現状と今後」
- 採用内定と雇用関係
- 老齢年金の「損・得」世代別試算について
- 障害者の法定雇用率引き上げ
- 政府の成長戦略構想と助成金の見直し
- 建設業の労働保険料が4割引!
- 10月から事業主の健康保険の扱いが変わります。
- 産前産後休業の話
- 最低賃金の話
- 外国人雇用と労務管理について
- 過重労働撲滅特別対策班
- テレワークという働き方
- 育児・介護休業法改正について
- パートタイマーへの社会保険適用拡大
- パートの制約条件
- SNSの発信を会社が取り締まることができるか
- 65歳以上への雇用保険の適用拡大
- 人生100年時代 ~新しい働き方と求められる能力~
- ユースエール認定制度
- 社会保険のパートへの適用拡大
- 産業医制度の変更点
- 平成29年10月施行 育児・介護休業法改正
- 雇用保険の基本手当日額
- ストレスチェックの 助成金
- 産前産後休業の保険料免除制度
- 社会保険の適用拡大
- 雇用保険の65歳以上への適用拡大
- 雇用保険の適用拡大(その2)
- 均衡待遇と均等待遇の違い
- 高額療養費と限度額適用
- パートタイマーへの労働条件の通知
- 雇用保険手続きのマイナンバー届出
- 従業員がマイナンバーの提供を拒否
- 月額変更の年間平均適用
- サマータイムの導入に必要な届出
- 外国人の雇用
- 扶養認定の厳格化
- 36協定の特別条項の上限
- 有給休暇の時季指定義務
- 70歳まで働ける機会を確保する
- 同一労働同一賃金
- 事実婚と扶養
- 離婚時の年金分割
- 新型コロナウイルスについてのQ&A
- 新型コロナウイルス感染時の傷病手当金
- コロナで労災申請はできるか?
- セクハラと労災
- 業務にLINEを活用しています
- 健康保険の被扶養者
- 教育訓練給付の拡充
- 働き方改革関連法
- 休業等があった場合の算定基礎届の考え方
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
- 令和2年度、被扶養者資格の再確認について
- お上はある日突然動く!
- 標準報酬月額の特例改定
- 休業手当を支給した月が含まれる場合の離職証明書の書き方
- 厚生年金保険の標準報酬月額、上限改定について
- パワハラ防止指針
- 社会保険の適用事業所と加入者について ~その1~
- 新型コロナウイルス感染時の傷病手当金受給について
- ワーキングホリデーで滞在する外国人の保険加入
- 失業保険はいくらもらえるか
- テレワーク時の時間管理について①
- テレワーク時の時間管理について②
- 雇用保険手続のマイナンバー届出
- 接骨院で保険は使えるか?
- マイナンバーカードの健康保険証利用について
- 出産や育児にかかる社会保険料の免除
- 自己都合退職の場合の給付制限期間の短縮
- 産休中の国民年金保険料免除
- 国民年金3号被保険者の今後
- 士業事務所の社会保険の適用要件が変わります
- 子の看護休暇と介護休暇の時間単位取得
- 副業・兼業の促進に関するガイドライン
- 新型コロナウイルス感染症の影響による離職者の離職証明書記載について
- 新型コロナウイルスの影響によるシフト減少で離職した場合の求職者給付
- 「男性版産休」の育児・介護休業法への新設について
- テレワークガイドラインの改定
- 新型コロナの影響による特例月額変更の延長
- 不妊治療の保険適用について
- 配慮すべき個人情報とは
- 労働審判という制度について
- 中小企業におけるパワハラ防止措置義務
- 雇用調整助成金の不正受給対応が厳格化されます!
- 複数の事業所で雇用される場合の社会保険等
- 外国人が帰国した際の年金はどうなる?
- 夫婦共同扶養の場合の被扶養者認定について
- 週休3日制の導入についての考察
- 複数の事業所で雇用される場合の社会保険
- 育児を理由とする短時間勤務制度の対象者
- 育児を理由とする短時間勤務制度の内容
- 社保適用拡大に合わせたパートタイマーへのヒアリングについて
- 一度体験したら二度と元のやり方に戻りたくなくなる便利な振込のやり方
- 10月分請求よりインボイスを発行します
- 有給休暇管理表の上手な作り方
- 福井MG 育児休業 好奇心
- ついに51人以上の企業のパートに社会保険の適用が拡大されます
- トランプ時代とMG
- トランプ・ゼレンスキー会談から学べること
- 信用とCFMG
法律守ってますか?
- 定年と再雇用の今を知る
- 社会保険の加入要件の話
- 36協定の話①
- 36協定の話②
- 年少者雇用の話
- 妊産婦雇用の話
- 労働時間の原則
- 休業手当の未払いにご用心
- 社会保険に加入しなければならない会社とは
- 従業員の健康診断
- なぜ裁判になると休業手当を100%支払うことになるのか?
- 減給の上限
- 外部の労働組合から団体交渉を申し込まれたら?
- 会社から一方的に給与を下げることはできるか?
- 社員が裁判員となった時の取り扱い
- 試用期間と契約期間
- 社会保険の調査で調べられること
- 賃金や労働時間などの労働条件は口頭の説明だけでよいか?
- ノーワーク・ノーペイの原則とは
- 「退職証明書」の話
- 親の介護で休みたいとの申し出があったら?
- 会社の「安全配慮義務」
- 必ず会社に保管しておかなければならない労務帳簿
- 雇用保険の手続を忘れてしまったら?
- 妊娠を理由に解雇してはいけません
- 健康診断の義務
- 管理職には残業代を支払わなくてもよい?
- 学生をアルバイトに雇う時の注意点
- 労災保険に入ってないのに労災事故が起きたら?
- 国民健康保険+厚生年金の社会保険
- 正社員とパートの格差は違法か?
- 派遣と出向
- 労働時間管理についての重要な通達「46通達」
- 労働時間の原則と例外
- 労働法の全体像は・・・
- 失業保険の話
- フルコミッション給与制度の問題点
- 定期健康診断やってますか?
- 台風などの天災で公共交通機関がマヒした場合、給与を支払うか?
- インターンの学生は労働者と何が違うか
- 研修時間に給与を支払う必要があるか
- ストレスチェックの義務化
- 妊産婦に関する労働基準法 その1
- 妊産婦に関する労働基準法 その2
- 割増賃金
- 掃除時間は労働時間か。
- 健康診断は会社の義務って本当?
- 零細企業でもわざわざ36協定を出さなくてはならないのか?
- 最低賃金を破るとどうなるか?
- パート、アルバイトの有給休暇
- 賃金の直接支払原則
- 会社の都合で社員に休んでもらった時に給料を払う必要があるか?
- 労働関係の書類の保存期間
- アルバイトやパートにも雇用契約書が必要か?
- 賃金の5原則
- 雇入れ時の健康診断
- 会社が行うべき健康診断の種類
- 健康診断の費用負担とその間の賃金
- 賃金の注意点
- パートの制約条件
- 事業所の社会保険適用状況がWEBで検索できる?
- 採用の自由と公正な募集
- 宿直・日直で気を付けること
- 平成29年10月施行 育児・介護休業法改正
- 36協定について
- 社員の健康診断
- 休憩時間中の「電話番」
- 管理監督者の条件
- 最低賃金に関する法律
- 社員を雇った時の書類
- 在宅勤務のみなし労働時間
- 夏休みや冬休みを有休消化日にできるか
- 社員旅行は労働時間か?
- アルバイトにも有休?
- 労務関係の書類保管
- 障害者雇用率制度
- 健康診断を実施後に会社がするべき事
- 休業手当
- 試用期間中の社会保険
- 夜勤者の健康診断
- 人事労務関係の書類の保管義務
- パートタイマーへの労働条件の通知
- ダブルワーカーを雇用した場合の時間外割増の計算
- 定期健康診断の報告
- 公正な採用
- 労働保険の年度更新
- 算定基礎届について
- 36協定
- 最低賃金と労働時間
- サマータイムの導入に必要な届出
- 労働条件の調査
- 従業員代表の適法な選出
- 労働時間の適正な把握&措置
- 賃金台帳と労働者名簿
- 子供を雇う時の注意点
- 外国人の雇用
- 産前産後の労働者への対応
- 振替休日と代休
- 転籍は拒否できるか
- 監視または断続的労働従事者の取扱
- 従業員への罰金制度は違法か?
- 試用期間の延長はできるか
- 台風で休業した時の休業手当
- 役員の社会保険加入
- 外国人を雇用する際の注意点
- 未払い残業代請求訴訟における「付加金」
- 障害者の法定雇用率
- 育児休業終了日と雇用保険上の取り扱いについて
- 非常勤役員の社会保険加入
- 休業等があった場合の算定基礎届の考え方
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
- 令和2年度、被扶養者資格の再確認について
- 労働保険料申告手続きを忘れたら?
- 労働者死傷病報告
- 育児休業中に有給休暇を取得可能か?
- 労働保険料の再確定申告
- 給与から控除できる項目
- 男性の育児休業の注意点
- 調査で判明する社会保険の誤解
- 別居している被扶養者の認定
- 自動車通勤者の通勤手当
- 労働安全衛生法の健康診断の種類
- 従業員が休憩を取らない代わりに、早く帰りたいと希望した時の対応
- フレックスタイム制における休日割増賃金
- 健康診断後の医師への意見徴収
- 平均賃金の基本的な考え方
- 労働基準法上の賠償予定の禁止
- 接骨院で保険は使えるか?
- 士業事務所の社会保険の適用要件が変わります
- 障害者の法定雇用率引き上げについて
- アルバイトの有休
- 産業医の選任
- 育児休業中の就労
- 70歳までの就業確保
- 64歳と65歳の失業保険の違いは?
- 資格喪失後の保険給付(健康保険)
- 労災で休業した日に賃金を払ったら休業補償の計算は?
- 労災保険の費用徴収
- 社宅を貸したときの所得税
- 定年後継続雇用期間の「無期転換ルール」の例外
- 複数の事業所で雇用される場合の社会保険
- 育児を理由とする短時間勤務制度の対象者
- 育児を理由とする短時間勤務制度の内容
- 割増賃金計算に算入すべき手当、除外可能な手当の概要
- 割増賃金計算に算入すべき手当、除外可能な手当の実態とは
- 労働時間把握のガイドライン(労働時間とは)
- 労働時間の把握ガイドライン(把握の方法)
- 労働時間の把握ガイドライン(自己申告の場合の措置)
- 派遣業の書類管理、大変ですよね?
- ついに51人以上の企業のパートに社会保険の適用が拡大されます
その他雑感
- 書籍の紹介(断食道場の先生の本「人間の頂」)
- 書籍の紹介(死ぬときに後悔すること25)
- 経営者らしいものの考え方(機会費用)
- iphone5を買いました
- モレなく、ダブリなく
- 経営者らしいものの考え方【比較優位】
- 知立市長選挙の公開討論会
- 私の趣味(どうでもいい、つまらない話)
- 断食道場
- 新年明けましておめでとうございます!
- 消費者目線で感じたこと(自転車購入)
- 「未来の働き方を考えよう(ちきりん著)」
- 心をコントロールする方法(書籍の紹介「やってのける」)
- なぜ社員は社長のように考えられないのか?(企業にとっての憲法論)
- 書籍の紹介「失敗の本質」
- グロービスマネジメントスクールに通ってます
- 永遠の0
- 開業8年目
- ゴルフの個人レッスン
- 経営者らしいものの考え方【サンクコスト】
- 経営者らしいものの考え方【機会費用】
- 経営者らしいものの考え方「囚人のジレンマ」
- 経営者らしいものの考え方【モラルハザード】
- 経営者らしいものの考え方【逆選択】
- 社労士がビジネススクールで学ぶ理由
- 慌てることと急ぐことの違い
- 感情を理解してコントロールする方法
- 「お金2.0」を読んでみた
- 人生100年時代 ~新しい働き方と求められる能力~
- 10年後の仕事図鑑
- MGの収穫⑤「主体性は教えることができない」
- 人生戦略は3つの資本で定義できる!
- 簿記3級を試験勉強一日でクリアする方法
- 業務にLINEを活用しています
- 通信手段の今昔(出版社時代の思い出)
- お上はある日突然動く!
- 社長、夜ぐっすり眠れてますか?
- zoomミーティングに対応いたします。
- 言葉に力を与えるもの
- 1200期達成おめでとうございます!
- お酒をやめましたが飲み会の誘いは大歓迎です。
- パワハラ対応で感じたこと
- 運命神ヤーンと出会いの法則について
- 長渕剛の「しあわせになろうよ」が持つ力
- パワハラ対応におけるTOC
- アイデア募集する側に求められる配慮とは?
- 一気飲み死亡事件をどうすれば無くせるか?
- ムダな振込手数料を払っていませんか?
- 一度体験したら二度と元のやり方に戻りたくなくなる便利な振込のやり方
- 子供の壁と行入のチカラ
- 給与計算はタテ割よりヨコ割が便利!
- 有給休暇管理表の上手な作り方
- 長浜MG~近江牛に想い出を添えて~
- 私とコンピュータ「ファイル名を自動入力する」
- M型職種とQ型職種
- ホテル時代の元上司の話
- 相談相手に必要なこと
- ある日のAIとの対話「信用の複利とウインウイン思考の可能性」
- トランプ時代とMG
- トランプ・ゼレンスキー会談から学べること
- 決断力の正体を探る
- 『八つ墓村』をめぐる冒険
- MG for students豊田 開催報告
- MG for students名古屋 開催
- 2004年クリスマスイブのすき焼き
- 能力と人格の関係